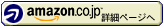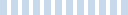| 読書状態: | 読み終わった | 期限日: | |
| カテゴリ: | 単行本 | 購入費: | 1620 円 |
| テーマ: | 未分類 | 入手日: | - |
| タグ: | 自動改札,, JR, | 読了日: | 2014/11/05 |
| 公開度: | 公開 | 評価: |  |
■ 蔵書メモ
自動改札機について書かれているのだが, 券売機や切符についても書いている。専門的な内容を平易に, 一般の読者にもわかりやすく説明していて, 別に鉄道に詳しくない僕でも理解出来るものなので良い。ICカードについても説明している。
* 自動改札機
関西の方が自動改札機の導入が早かった。NRZ-1方式とFM方式とがあり, 不正乗車問題を解決するなどの方面から, 各社が恣意的に運用していた方式を旧NRZ-1方式からFM方式に転換し, 一本化することが求められrた。不正乗車問題は鉄道イメージとも結びつくので, 近年でも問題視されているこことがらである。対策はいくつか考えられる。物理方面では, 自動改札機のドアをどうするかということがある。欧米では全面的に不正乗車を阻止するという考え方があって, ハードドア方式を使っているところがある。ただ, 電車内で乗務員が点検し, 余分に払わせる方法を取ることで不正乗車を予防することにもなっているようで, これは日本でも採用されている。日本の場合, 不正乗車は定額の三倍の料金を払わせることをJRの利用規程としていて, 自動改札機では改札通過などの時間を切符に記録することで不正乗車を阻止している。
* サイバネ規格
近距離(100kmまでの)切符ではエドモンソン券で, 別に定期券サイズのものがあり, これをサイバネ規格という。2つの規格を共通で使っているのは, そうすることが全体的にコストダウンだからであるらしく, いまだに2つのサイズが併用して用いられている。この規格が出た当初は某国会議員から不満の声が出たなどというが, いまはあまり聞かれない。切符の裏が黒色のものが自動改札機で利用可能なものだが, これは黒色がもっとも磁気を保有するためで, 昔は茶色だったという。
SuicaなどのICカードが出始めた当初の本なので, いま問題となっているIC規格や交通電子マネーの共通化, 一本化についてはまったく触れていない。が, JR各社が採用してきた方式を統一のものとすることは, 協議に時間が掛かり過ぎること, IC専用の自動改札機に手を加えないといけないこと(費用が掛かり過ぎること), Suicaには専用のサーバがあるらしく, ICカードで用いるバックグラウンドの技術運用をどうするか, など問題が山積しているように感じる。
おもしろいのは, 香港では2000年にICチップを埋め込んだ腕時計型の端末が限定で出たということで, いまiWatchやサムソンほか各社が似たような腕時計型端末を出しているがどうなるのか。混雑することは目に見えているし, 改竄されやすくコストもリスクもかかる端末をJRがゆるすか, と思うのだけれど, ICカードが費用低減に貢献するのだとしたら, そもそもカード媒体で出す必要はないのだと思う。
目次
■ 目次メモ
(まだ目次メモはありません)
進捗記録
|
[2014/11/11] (0~0ページ) |